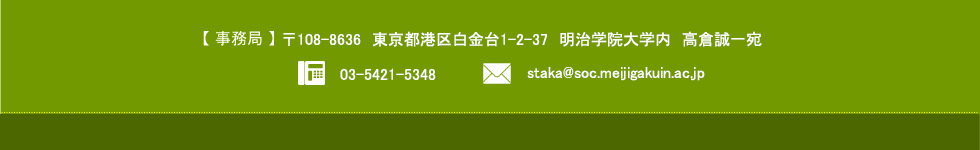日本生活中心教育研究会
- 日本生活中心教育研究会
- 研究会開催
再開!第2回知的障がい教育のしくみを学ぶ会
- ○開催日時:2026年1月24日(土)14:00~16:00
- ○会場:明治学院大学(白金)1302教室
- ○参加費無料。オンラインあり。
- ○お申し込み、チラシはこちら。
2026年01月22日掲載
第25回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○開催日時:令和8年2月14日(土)18時から
- ○会場:葉山高知市はりまや町1丁目6-1
- ○話題提供高知市立朝倉小学校 齋藤 望 先生「幅広滑り台で遊ぶ」(全特連機関誌 R8 2月号)高知市立昭和小学校 井上 翔平 先生「千日紅で交流及び共同学習」(学研機関誌 R8 3月号)高知市立朝倉第二小学校 坂下 あき 先生「身近で防災活動を」(全特連機関誌 R7 7月号)高知市立城西中学校 下元 美樹 先生「校外で合同販売会」(生活中心教育研究会機関誌 R7)
- ○その他
実践のプリントや掲示物、年間計画、紹介する資料、制作物、製品等があればお持ちください。販売もOKです。
- ○お申し込み、チラシはこちら。
2026年01月20日掲載
第24回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○開催日時:令和8年2月14日(土)18時から
研究会13:30~16:30 懇親会17:00~19:00
- ○会場:葉山(高知市はりまや町1丁目6-1)
- ○申し込みとチラシはこちら。
2025年12月22日掲載
日本生活中心教育研究会第27回大会「千葉大会」
- ○開催日時:令和8(2026)年2月21日(土)
研究会13:30~16:30 懇親会17:00~19:00
- ○会場:植草学園大学内 さくらホール(〒264-0007 〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3)
- ○参加費:研究会1.500円(学生無料) フォーラム(懇親会)4.000円
- ○開催形態:対面とオンラインのハイブリット(オンライン参加は無料
- ○申し込みとチラシはこちら。
2025年12月15日掲載
第19回子ども主体の知的障害教育を学ぶ会
- ○日時:2026年1月31日(土)13:30~16:30
- ○会場:岩手大学教職大学院棟2階(オンラインあり)
- ○参加費:無料
- ○申込締切:1月29日(木)
- ○チラシと申込みはこちら。
2025年12月04日掲載
再開!「しくみを学ぶ会」
- ○日時:2025年11月29日(土)14時~16時
- ○会場:明治学院大学1254教室(オンライン同時開催)
- ○参加費:無料
- ○チラシと申込みはこちら。
2025年11月06日掲載
第18回やまがた子ども主体の授業実践を考える会in天童
- ○テーマ:子ども達の豊かな生活の実現に向けてpart2
~再考、「知的障がい教育」の基礎・基本と実際~
- ○日時:2025年10月11日(土)10:00~15:00
- ○会場:山形県総合運動公園 屋内プール付属施設 P1会議室
- ○参加費:2000円
- ○申し込み https://forms.gle/iFpC8PFxSjU2p1HZA
- ○チラシはこちら。
2025年09月18日掲載
日本特殊教育学会第63回大会での会員による自主シンポジウムの開催について
- ○日時:2025年9月13日(土)~15日(月・祝)
- ○会場:水戸市民会館(茨城県水戸市泉町1-7-1)
- ○9月13日(土)15:00~16:30「各教科等を『合わせた指導』の今日的な意義を考える」
- 企画・司会者 高倉誠一(明治学院大学)
- 話題提供者 髙瀬浩司(植草学園大学) 柴垣登(岩手大学) 高倉誠一(明治学院大学)
- 指定討論者 戸屋 学(山形県教育局特別支援教育課) 佐藤愼二(植草学園大学)
- ○9月14日(日)8:30~10:00「今、知的障害の子たちの『生活を大事にする教育』の意味とは?」
- 企画・司会者 髙瀬浩司(植草学園大学) 太田俊己(放送大学)
- 話題提供者 千葉秀雄(前千葉市立金沢小学校) 千葉雅弘(前多賀城市立山王小学校)
- 栗田朋寛(山形県立米沢養護学校)
- 指定討論者 戸屋学 (山形県教育局特別支援教育課)$00A0 髙瀬浩司(植草学園大学)
2025年09月03日掲載
第24回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○日時:令和7年8月4日(月)18時30分から
- ○会場:高知会館(高知市本町1丁目6-1)
- ○話題提供:
YouTuber チーバちゃんねる 元校長 千葉 秀雄さん
この春退職後、特別支援教育の面白さと魅力を発信中の方です。きっと面白い!! - ○講話:
明治学院大学准教授 高倉 誠一 さん - ○KUMIちゃん講座:
弁護士 中橋 紅美 さん テーマ「知的障害・発達障害のある人の責任能力の考え方」 - ○お申し込み、チラシはこちら
2025年07月07日掲載
日本生活中心教育教育研究会第27回大会「千葉」大会(第一報)
- ○開催日:令和8(2026)年2月21日(土)
- ○会場:植草学園大学 https://www.uekusa.ac.jp/page-101009/access
2025年06月02日掲載
第23回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○日時:令和7年2月8日(土)17時30分から
- ○会場:葉山(高知市はりまや町1-6-1)
- ○話題提供:
- ・「高等部の作業学習について」
高知特別支援学校高等部主事 岡林 浩祐 さん - ・「鶴文字の作り方の実際」
高知市立一宮小学校教諭 谷 雄二 さん
- ・「高等部の作業学習について」
- ○講話
- 明治学院大学准教授 高倉 誠一 さん
- ○その他
- いつものことですが、実践のプリントや掲示物、年間計画、紹介する資料、制作物、製品等があればお持ちください。みんなの宝物になっていきますね。販売もOKです。
- ○お申し込み、チラシはこちら
2025年02月03日掲載
令和6年度第3回学習会「いしかわ生活単元学習を学ぶ会」
- ○日時:令和7年2月22日(土)13:30~16:30
- ○金沢大学附属特別支援学校(リモート参加もOK)
- ○実践発表:
- ・金沢市立額小学校 薄井 純子 先生・池田 亜樹 先生
- 「物語のせかいからとび出して」
- ・能美市立寺井小学校 宮本 聖蘭 先生
- 「ハロウィンパーティーをひらこう」
- ・金沢市立額小学校 薄井 純子 先生・池田 亜樹 先生
- ○講演:
- 全日本特別支援教育研究連盟 理事長
植草学園大学 名誉教授
名古屋 恒彦 先生
「単元設定と授業展開のポイント」
- 全日本特別支援教育研究連盟 理事長
- ○参加費:無料
- ○お申し込み、チラシはこちら
2025年01月27日掲載
第18回子ども主体の知的障害を学ぶ会
- ○主催: いわて子ども主体の知的障害教育を学ぶ会
(共催: やまがた子ども主体授業実践ネットワーク) - ○日時: 令和 7 年 2 月1 日(土)13:30~16:30
- ○会場: 岩手大学教職員大学院2階・オンラインもあり
- ○実践発表:
- ① 小学部「遊びの指導」
- 皆川 咲恵 先生(岩手県立前沢明峰支援学校)
- ② 中学部「作業学習」
- 及川 高生 先生(岩手県立盛岡みたけ支援学校奥中山校)
- ③ 小学部「生活単元学習」のリフレクション(授業の振り返り)による授業改善の検討
- 小林 美奈子 先生(岩手県立久慈拓陽支援学校)・佐々木 全 先生(岩手大学大学院教育学研究科 准教授)
- ① 小学部「遊びの指導」
- ○全体のまとめ:
名古屋 恒彦 先生(全日本特別支援教育研究連盟 理事長) - ○申込締切: 令和7年1月28日(火)
- ○参加費: 無料
- ○チラシはこちら
2025年01月16日掲載
日本生活中心教育研究会第27回大会「千葉大会」
- ○日時:令和7(2025)年2月22日(土)13:00~16:10
- ○会場:植草学園大学さくらホール
- ○実践発表:
- 「小学部・小学校の先生に手紙を送ろう~中学生になった自分たちを紹介~」
- 千葉県立千葉特別支援学校 山田里苗先生
- 「オグリクラフト~モザイクアートで巨大壁画づくりに挑戦!~」
- 船橋市立小栗原小学校 伊藤杏子先生
- 「小学部・小学校の先生に手紙を送ろう~中学生になった自分たちを紹介~」
- ○シンポジウム: 「千葉から発信!各教科等を合わせた指導の今後の展望」
- ○申し込み https://forms.gle/LBASkJrrbfmuVbzv6
- ○チラシはこちら
2024年12月25日掲載
令和6年度第2回学習会「いしかわ生活単元学習を学ぶ会」
- ○日時:11月23日(土) 9:30~12:30
- ○会場:金沢市立中央小学校芳斎分校(※リモート参加もOK)
- ○実践発表:
- ・金沢市立戸板小学校 順教寺 文代 先生
- 「星にねがいを七夕まつりをしよう~みんなで楽しもう~」
- ・金沢市立押野小学校 新出 真奎 先生
- 「みんなでお出かけにいこう」
- ・金沢市立戸板小学校 順教寺 文代 先生
- ○講演:
- 全日本特別支援教育研究連盟 理事長
植草学園大学 名誉教授
名古屋 恒彦 先生
「各教科等を合わせた指導」と各教科の学習内容の関連性
- 全日本特別支援教育研究連盟 理事長
- ○参加費:無料
- ○お申し込み、チラシはこちら
2024年11月08日掲載
第17回やまがた子ども主体の授業実践を考える会
- ○期日:令和6年11月2日(土)
- ○時間:10:00~15:50 (受付 9:30~)
- ○会場:鼠ヶ関公民館 第1研修室
- ○実践報告
- ・白畑 恵里子先生(酒田特別支援学校)
- ・佐藤 史也先生(米沢養護学校)
- ○講演「子どもたちの豊かな生活の実現に向けて」
- ・講師 植草学園大学 発達教育学部 准教授 高瀬 浩司先生
- ○参加費:500 円
- ○お申し込み、チラシはこちら
2024年10月04日掲載
第22回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○日時:令和6年8月5日(月)18時15分から
- ○会場:高知会館( 高知市本町5丁目6-42)
- ○話題提供:
- 知的障害特別支援学級担任として,5年目を迎えて思うこと
高知市立朝倉第二小学校 坂下 あき 先生
- 知的障害特別支援学級担任として,5年目を迎えて思うこと
- ○一言・二言コーナー:
- ・中坪 晃一さん(植草学園短期大学名誉教授・「りぐる会」遠隔地会員)
- ・太田 俊己さん(放送大学客員教授・「しくみを学ぶ会」世話人)
- ○KUMIちゃん講座
- 「LGBTQ+について」 弁護士 中橋 紅美 さん
- ○お申し込み、チラシはこちら
2024年06月28日掲載
令和6年度第1回 いしかわ生活単元学習を学ぶ会
- ○日時:7月20日(土)13:30~16:30
- ○会場:石川県立小松特別支援学校
- ○実践発表:
- 「働くってどんなこと?~みんなの周りの働く人~」
石川県立小松特別支援学校 水間 有香 先生 - 「ひなたカフェをひらこう~本気で取り組める本物の活動を目指して~」
山形県立米沢養護学校 安部 遼平 先生
- 「働くってどんなこと?~みんなの周りの働く人~」
- ○講演:
- 「生活単元学習の魅力と授業づくりのポイント」
全日本特別支援教育研究連盟 理事長・植草学園大学 名誉教授 名古屋 恒彦 先生
- 「生活単元学習の魅力と授業づくりのポイント」
- ○申し込み、チラシはこちら
2024年06月28日掲載
第4回「しくみを学ぶ会」
- ○日時:2024年6月8日(土)14:00~16:00
- ○会場:明治学院大学1505教室(オンラインとのハイブリット開催)(見逃し録画配信あり)
- ○会費:無料
- ○チラシとお申し込みはこちら
2024年06月04日掲載
第3回「しくみを学ぶ会」
- ○日時:2024年4月20日(土)14:00~16:00
- ○会場:明治学院大学1505教室(オンラインとのハイブリット開催)(見逃し録画配信あり)
- ○会費:無料
- ○チラシとお申し込みはこちら
2024年04月02日掲載
日本生活中心教育研究会 第26回オンライン総会・研究会
- ○期日:2024年2月17日(土)10:00~11:30
- ○内容:
- <総会>10:00~10:30 令和5年度事業報告及び令和6年度事業計画について
- <研究会>10:30~11:30 研究会 (動画での発表となります)
- 生活単元学習「行こう!乗ろう!やってみよう!」
- 島扇径子先生(米沢市立東部小学校)
- ○お申し込みはこちら(別ウインドウが開きます)
2024年02月05日掲載
令和5年度第3回 いしかわ生活単元学習を学ぶ会
- ○日時:令和6年 2月23日(金・祝)13:30~16:30
- ○会場:石川県立小松特別支援学校 多目的室
- ○参加費:無料
- 〇会場×リモート ハイブリット開催
- ○実践発表:
- 「ようこそ!お化け屋敷へ!」金沢市立米丸小学校 荒木 弥生子 先生
- 「生徒が考えたくなる作業学習を目指して」石川県立錦城特別支援学校 山本 桂 先生
- ○講評:
- 全日本特別支援教育研究連盟理事長 名古屋 恒彦 先生
- 「生活単元学習の指導計画の立て方」
- ○申し込み、チラシはこちら。
2024年01月25日掲載
第21回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○期日:令和6年2月23日(金) 午後6時から
- ○会場:「葉山」 高知市はりまや橋1-6-1
- ○話題提供:
- 生徒主体の作業学習に取組み,合同販売会へ繋げた実践
高知市立城西中学校 下元 美樹 さん
- 生徒主体の作業学習に取組み,合同販売会へ繋げた実践
- ○懇親会
研修がひと段落つけば,「お客」(懇親会)です。恐れ入りますが、5,000円費用を要します。
- ○お申し込み:
申し込み:りぐる会会長 西岡ゆき子
ケータイ:080-5011-1560
パソコン:yukiko.nishioka1025@gmail.com - ○チラシはこちら。
2024年01月23日掲載
第2回「しくみを学ぶ会」
- ○期日:2024年2月10日(土)14:00~16:00
- ○会場:明治学院大学1505教室(オンラインとのハイブリット開催)
- ○参加費:無料
- ○世話人:
- 太田俊己(放送大学客員教授)、高倉誠一(明治学院大学教授)、中坪晃一(植草学園短期大学名誉教授)
- ○チラシと申し込みはこちら。
2024年01月23日掲載
子ども主体の学校生活づくり講演・学習会講演・学習会 in 多賀城
- ○期日:令和6年1月20日 第一部10:00~11:50 第2部13:30~15:30
- ○会場:宮城県多賀城市中央公民館(文化センター内)
- ○第一部:
- 「特別支援教育研究』編集委員・千葉市立金沢小学校長 千葉 秀雄 先生
『テーマのある学校生活づくりとできる状況づくり ~基礎から学ぶ「生活単元学習」・「作業学習」~』
- 「特別支援教育研究』編集委員・千葉市立金沢小学校長 千葉 秀雄 先生
- ○第二部:
- みやぎ・ひまわりの会会長(松島町立松島第五小学校 教諭)上野 庸悦 先生
『特別支援学級12か月~そうなんですか?そうなんですよ~』
- みやぎ・ひまわりの会会長(松島町立松島第五小学校 教諭)上野 庸悦 先生
- ○チラシはこちら。
2023年12月27日掲載
第1回 知的障がい教育のしくみを学ぶ会(報告)
12月16日(土)15時~17時、会場(明治学院大学)とオンラインのハイブリッド方式で開催。全国からの160名以上もの参加者がありました。
知的障がいの子どものよさの発揮を支援する「しくみ」のある知的障がい教育。この柔らかな「しくみ」を面白く学び、子どもが生き生きとりくむ実践を支えていきましょうと、説明があった後、テーマの話に。
テーマは「生活単元学習と作業学習のルーツを確かめよう」。70年以上前、知的障がい生徒のみ在学する東京都立青鳥中学校で行われた4か月にわたる「バザー単元」。この単元で生徒も先生も保護者もバザーの成功に向け、夏休み返上で働いた単元・生徒たちの取り組みが紹介され、当時の熱気とその後の生活単元学習の確立につながる意義と成果が語られました。あとのグループ話し合いでは、各地の販売会での成果や作業・生単の実践などの話題が。元気な声と実践の様子がたくさん聞かれたよい会となりました。
次回は2月10日(土)午後。今日の個別最適な学び・協働的な学びにも通じる、「個別化と集団化」の実践(過去の千葉大学附属養護学校の実践研究)を話題にします。ご参加をお待ちしています!

ズームで意見の交換 会場の様子
- ○見逃し配信(録画)は以下から。(2月9日まで視聴可)
技術的問題で、初めの15分が録画もれ、休憩時・最終時はむだな画面があります。お許しください。
https://drive.google.com/file/d/1vmfEpsbSIubsRv4iNKmKUNHfis-JCccw/view?usp=drive_link
2023年12月20日掲載
第17回子ども主体の知的障害教育を学ぶ会
- ○期日:令和6年2月3日(土)13:30~16:45
- ○会場:岩手大学教職大学院棟2階(オンラインもあり)
- ○基調講演:
- 「子ども主体の知的障害教育とは 」
- 名古屋恒彦 先生(全日本特別支援教育研究連盟理事長)
- ○実践発表
- 特別支援学校小学部「生活単元学習アートフェスティバルをしよう 」
藤田ちひろ 先生(岩手県立盛岡ひがし支援学校) - 特別支援学校 中学部「分教室における交流及び共同学習の実践 」
坪谷有也 先生(岩手県立花巻清風支援学校北上みなみ分教室)
- 特別支援学校小学部「生活単元学習アートフェスティバルをしよう 」
- ○お申し込み:締め切りは令和6年1月26日(金)。参加費は無料です。
申し込み方法も含めて、こちらをご覧ください。
2023年12月05日掲載
第1回 知的障がい教育の「しくみを学ぶ会」
- ○期日:令和5年12月16日(土)15:00~17:00
- ○会場:明治学院大学1501教室(オンラインとのハイブリット開催)
- ○世話人:
- 太田俊己(放送大学客員教授)、高倉誠一(明治学院大学教授)、中坪晃一(植草学園短期大学名誉教授)
- ○参加費:無料
- ○チラシはこちら。
2023年11月06日掲載
いしかわ生活単元学習を学ぶ会 令和5年度 第1回学習会
- ○期日:令和5年11月25日(土)13:00~16:00
- ○会場:金沢大学附属特別支援学校
- ○実践発表:
- 「まつり ドッキリ 楽しむぞ!!」能美市立寺井小学校 水島 裕子 先生
- 「作ってあそぼう ~ 夏祭りをしよう!~」金沢市立戸板小学校 大井山 恵 先生
- ○講評・講話:
- 金沢星稜大学 人間科学部講師 柳川 公三子 先生
- ○お申し込み・参加費:
- 申し込み締め切りは11月10日(金)。参加費は無料です。
- ○チラシはこちら。
2023年10月27日掲載
第20回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
- ○期日:令和5年8月4日(金)18:15~
- ○会場:高知会館 〒780-0870 高知市本町5-9-42
- ○話題提供ほか:
- 「小学校の生活単元学習 ~ 遊び単元の進め方 実践を通して」
高知市立一宮小学校 谷雄二 さん
- 「小学校の生活単元学習 ~ 遊び単元の進め方 実践を通して」
- ○懇親会
取組をじっくり話し合ったり、二学期以降の実践について意見を交換したり収集したり、ただただ仲良くなったり……(会費5,000円)
- ○お申し込み:
会長の西岡先生へ直接に!
ケータイ:080-5011-1560
パソコン:yukiko.nishioka1025@gmail.com - ○チラシはこちら。
2023年07月13日掲載
やってみよう!生活単元学習 いしかわ生活単元学習を学ぶ会 令和5年度 第1回学習会
- ○期日:令和5年7月29日(土)13:00~16:00
- ○会場:金沢市立中央小学校 芳斎分校
- ○実践発表:
- 石川県立七尾特別支援学校 向田 伸平 先生
「行こう!高等部へ!~中3学習発表会から卒業までの実践について~」
- 石川県立小松特別支援学校 谷下 加奈 先生
「お店を開こう! ~遊びランドにいらっしゃい~」
- 石川県立七尾特別支援学校 向田 伸平 先生
- ○講演:「各教科等を合わせた指導における学習評価」
全日本特別支援教育研究連盟理事長・植草学園大学名誉教授 名古屋 恒彦 先生
- ○お申し込み・参加費:
参加費は無料です。
<会場参加>事前申し込み不要です。直接会場にお越しください。
<リモート参加> 申込フォームよりお申し込みください ⇒ https://forms.gle/bj1aCJWEEm8mcnyz6
締め切りは7月23日(日)。 - ○チラシはこちら。
2023年07月13日掲載
日本生活中心教育研究会 第26回大会「やまがた大会」(第二次案内)
- ○主催:日本生活中心教育研究会
- ○共催:やまがた子ども主体の授業実践を考える会(実行委員会事務局)
- ○期日:令和5年9月17日(日)
- ○会場:
山形テルサ (https://yamagataterrsa.or.jp/)
JR山形駅西口より徒歩4分。近隣にホテルも多数あります。
- ○参加費:研究会は1000円 懇親会5000円
- ○その他:
チラシと申し込みはこちら
大会の報告はこちら
2023年10月11日更新
2023年08月02日更新
2023年05月15日掲載
やってみよう!生活単元学習 いしかわ生活単元学習を学ぶ会 令和4年度 第3回学習会
- ○期日:令和 5 年 2 月 25 日(土)13:00~16:00
- ○主催:いしかわ生活単元学習を学ぶ会
- ○実践発表:
- ①「対人コミュニケーションスキルの向上を目指した指導・支援~接遇・マナー教室の実践について~」石川県立いしかわ特別支援学校 澤田絵梨奈 先生
- ②「モチベーションを高めてやる気を引き出す取り組み ~食品加工の実践について~」石川県立明和特別支援学校 中川 伸明 先生
- ○講演:「本気で取り組む作業学習」植草学園大学 教授 名古屋 恒彦 先生
- ○お申し込み:添付チラシをご覧ください。締め切りは2月17日(金)。参加費は無料です。
2023年01月17日掲載
いわて子ども主体の知的障害教育を学ぶ会 第16回研究会
- ○期日:令和 5 年 2 月 4 日(土)13:30~16:30
- ○主催:いわて子ども主体の知的障害教育を学ぶ会
共催:やまがた子ども主体授業実践ネットワーク - ○実践発表:
- ①特別支援学校小学部 生活単元学習「すきすきかみすき④ すきすきかみすきやさんをひらこう」 小山 聖佳 先生(岩手県立盛岡みたけ支援学校)
- ②特別支援学校高等部 作業学習「わくわくバザーに向けて製品を作ろう」谷口 輪 先生(山形県立鶴岡養護学校)
- ○講評:岩手大学 大学院教育学研究科 准教授 佐々木 全 先生
- ○講演:「各教科等を合わせた指導のこれから」
植草学園大学 発達教育学部発達支援教育学科 教授 名古屋 恒彦 先生 - ○お申し込み:添付チラシのメールアドレスからお申し込みください。締め切りは1月20日(金)。参加費は無料です。
2023年01月16日掲載
日本生活中心教育研究会 第25回オンライン総会・研究会
- ○期日:2023年2月18日(土)10:00~11:30
- ○内容:
- <総 会>10:00~10:30 事業・会計報告及び来年度の方向性について
- <研究会>10:30~11:30 研究会(実践発表)
『本物のやりがいと手応えを~地元の伝統産業を取り入れた作業学習の展開~』
栗田 朋寛先生(山形県立米沢養護学校)
2022年12月19日掲載
やってみよう!生活単元学習
令和4年度令和4年度「第2回いしかわ生活単元学習を学ぶ会」の開催について
- ○期日:2022年11月26日(土)13:00~16:00
- ○会場:明和特別支援学校(リモート・ハイブリッド開催)
- ○参加費無料:無料
- ○実践報告:
- 「つくって あそぼう!わくわくタイム」金沢市立戸板小学校 林早紀 先生
- 「さつまいもの収穫パーティーをしよう」金沢市立押野小学校 亀田晶子 先生
- ○講演:「一人ひとりが活躍する集団の授業づくり」植草学園大学教授 名古屋恒彦 先生
- ○参加方法:詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
2022年11月01日掲載
第18回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
とにかく、情報交換をしましょう。手応えのあった単元のことはもちろん、暗くなる事象、うまくいかない学級経営、みんなどうしてるのかなあ・・等々,いつものように語り合いましょう。実践のプリント類も持ち込みOK!!みんなで共有しましょう。
- ○日時:8月5日(金)18:00~
- ○場所:「葉山」高知市はりまや橋1-6-1(電話088-882-6670)
- ○内容や申込先:こちらのチラシをご覧ください。
2022年06月27日掲載
日本生活中心教育研究会第25回大会 石川大会「今こそ高めよう、広げよう 生活中心教育の実践」
今大会は、石川県のみならず富山県、福井県からも実践発表があり、実際には「北陸大会」とも言えるものです。これを機に北陸地区で志を同じくする者のつながりを強めるとともに、全国の皆さんとの結びつきも強化し、子ども主体の生活中心教育をますます充実させてまいりましょう。感染対策をしっかり行い、対面での開催を基本としますが、現在の感染状況も考慮してオンラインでの参加も可能としました。皆様の参加を心からお待ちしています。(いしかわ生活単元学習を学ぶ会一同)
- ○期日:2022年8月27・28日(土・日)
27日(土)13時開会~28日(日)12:30閉会 - ○会場:金城大学笠間キャンパス
- ○日程や内容: こちらの案内PDFをご覧ください。
- ○参加費、交流会、宿泊の申し込み要項: こちらの案内PDFをご覧ください。
- ○申し込み方法: こちらの申込書(エクセル)に入力のうえ、下記までメール添付にてお願いします。
※「安全にダウンロードできません」という警告がでた場合は、こちらの資料をご参考下さい。 - <大会申込書送信先>
株式会社トラベル・エー taikai@travel-a.net※申込締切り 7月8日(金)
2022年06月03日掲載
日本生活中心教育研究会第24回大会の開催について
- ○期日:2022年2月19日(土)13:30~16:30
- ○テーマ:子どもが主人公!主体的に取り組む生活の実現~生き生き活動する姿を求めて~
- ○内容:
【実践発表1】 単元「みんなで遊ぼうくすのきリンピック」
岡﨑 暁子先生 (金沢市立戸坂小学校教諭)【実践発表2】単元「高知の池選手と車いすラクビーチーム『フリーダム』を応援しよう」
汲田 喜代子先生 (高知県高知特別支援学校教諭) - ○チラシはこちら
会員の方は、郵送でお送りしたチラシにパスワードが記載してあります。 - ○申し込みはこちら(別ウインドウが開きます)
2021年12月09日掲載
- ※「申し込みページ」に研究会当日の配付資料を掲載しました(2022/2/16追記)
- ※第24回大会の遠隔開催へのご参加方法について(2022/2/14追記)
- ○第23回大会は、遠隔会議システムの「zoom」を使用して開催します。参加方法につきましては、「申し込みページ」で手続きをされますと、接続先のURLとパスコードが表示されますので、当日にアクセスをお願いします。なお、「申し込み」にあたっては、別途郵送でお送りしたチラシに記載の4桁数字のパスワードが必要になります。
- ○「総会」からご参加の方は13:30以降に、「研究会」からご参加の方は13:45以降にアクセスをお願いします。
- ○「申し込み」は何度でも可能です。zoomのURLやパスコードがわからなくなった場合は、改めてお申し込み手続きをお願いいたします。
- ○ご不明なことなどございましたら、お手数ですが、下記アドレスまでご連絡ください。
(事務局 高倉:staka@soc.meijigakuin.ac.jp)
「令和3年度 第2回 やってみよう!生活単元学習」開催について
- ○期日:2021年11月27日(土)13:00~16:00
- ○会場:金沢大学附属特別支援学校
- ○内容:【実践報告】
- 「身体の名前を覚えよう」 七尾特別支援学校教諭 能﨑恵輔先生
- 「学習発表会で伝えよう~スイミーもうひとつの物語~」 金沢大学附属特別支援学校教諭 大矢栄子先生
【講演】
「子どもたちが動きたくなるテーマ設定のコツ」 植草学園大学教授 名古屋恒彦先生 - ○参加費は無料です。チラシや申し込み方法などはこちら
2021年11月02日掲載
「令和3年度 第1回 やってみよう!生活単元学習」開催について
- ○期日:2021年8月28日(土)13:00~16:00
- ○会場:
石川県立いしかわ特別支援学校
今般の感染拡大を受け、オンライン開催のみとさせていただきます(8/5更新) - ○内容:【実践報告】
- 「みんなで遊ぼうくすのきリンピック」 金沢市立戸板小学校 岡﨑暁子先生
- 「きてほしいな、ワジマーお化けランド~作りたくなる、遊びたくなる素材遊び~」
明和特別支援学校小学部 中谷亮介先生
【講演】
『各教科等を合わせた指導』と教科の『見方・考え方』との関連性について
植草学園大学教授 名古屋恒彦先生 - ○参加費は無料です。チラシや申し込み方法などはこちら
2021年08月04日掲載
2021年08月05日更新
「第3弾 やってみよう!生活単元学習in金沢」を開催について
- ○期日:2021年2月27日(土)13:00~16:00
- ○会場:石川県立いしかわ特別支援学校
- ○内容:【実践報告】
- 作業学習「ものづくりの観点から見る作業学習」
- 作業学習「働くことのよろこびややりがいを感じるために~高等部作業 窯業班での取り組み~
- 生活単元学習「分けない指導を目指した集団遊び」
【講義】
各教科等を合わせた指導における「主体的・対話的で深い学び」
植草学園大学教授 名古屋恒彦先生 - ○参加費は無料です。チラシや申し込み方法などはこちら
2021年02月12日掲載
日本生活中心教育研究会第23回大会の開催について
- ○期日:2021年2月20日(土)13:30~16:30
- ○会場:今般の緊急事態宣言の延長を受け、遠隔(zoom)のみでの開催
- ○テーマ:再考 知的障害教育―テーマのある学校生活の再出発―
- ○内容:
【実践発表】 単元「もっこうやさんになろう!」
向野紀子先生(船橋市立高根台第三小学校教諭)【実践発表】 単元「めざせ! アウトドアの達人!!」
赤間 樹先生 (千葉県立印旛特別支援学校教諭)【講 演】 「テーマのある学校生活の再出発」
関東学院大学教授 太田俊己 先生 - ○チラシはこちら
※リモート参加に使用するパスワードについては、会員のみとなりますので、除いてあります。
会員の方は、郵送でお送りしたチラシにパスワードが記載してありますので、それをご覧ください。 - ○申し込みはこちら(別ウインドウが開きます)
第23回大会の遠隔開催へのご参加方法について
- ○第23回大会は、zoomを使用して開催します。参加方法につきましては、「申し込みページ」で手続きをされますと、接続先のURLとパスコードが表示されますので、当日にアクセスをお願いします。なお、「申し込み」にあたっては、郵送のチラシに記載の4桁数字のパスワードが必要になります。
- ○「総会」からご参加の方は12:50以降に、「研究会」からご参加の方は13:20以降にアクセスをお願いします。
- ○「申し込み」は何度でも可能です。zoomのURLやパスコードがわからなくなった場合は、改めてお申し込み手続きをお願いいたします。
- ○ご不明なことなどございましたら、お手数ですが、下記アドレスまでご連絡ください。
(機器担当 高倉:staka@soc.meijigakuin.ac.jp)
2021年02月04日更新
2020年12月22日掲載
第15回「とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会 (通称、りぐる会)」開催報告
令和元年12月14日(土)に開催されました「第15回りぐる会」の報告です。
※詳しくはこちら。
2020年01月15日掲載
「第3弾 やってみよう!生活単元学習in金沢」を開催について
- ○期日:2020年2月22日(土)9:30~12:30
- ○会場:石川県立いしかわ特別支援学校
- ○内容:実践報告1「夏祭りをしよう!」
実践報告2「生徒の思いをロゴと製品に~縫製班の取り組み」
講義「確かな学びを実現する『リアルの教育学』」
植草学園大学教授 名古屋恒彦先生 他 - ○参加費は無料です。チラシや申し込み方法などはこちら
2019年11月18日掲載
日本生活中心教育研究会第22回大会の開催について
- ○期日:2019年12月21日(土)13:30~15:25
- ○会場:植草学園大学 L棟10・11講義室
- ○テーマ:実践 生活単元学習 作業学習―子ども主体の学校生活・授業づくり―
- ○内容:小学校知的障害特別支援学校から生活単元学習の実践報告
知的障害特別支援学校から作業学習の実践報告
分科会 など - ○チラシや申し込み方法などはこちら
※研究会会員の方は、参加費1000円となります。こちらの申込用紙をお使いください。
2019年11月01日掲載
第15回 とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会(通称りぐる会)の開催について
- ○期日:2019年12月14日(土)18:00~
- ○会場:「葉山」高知市はりまや橋1-6-1
- ○内容:小学校知的障害特別支援学級の生活単元学習の実践報告
弁護士は見た!
船橋の隠居爺の独り言 など - ○チラシや申し込み方法などはこちら
2019年11月01日掲載
6月1日(土)に、14回となる高知県での研究会、「とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会 (通称、りぐる会)」が開催されました!
令和元年6月1日(土)に開催されました「第14回りぐる会」の報告です。
参加者は28名(特別 支援学校関係10名,特別支援学級関11名,県職員1名,教育研究所関係2名,そして助言者・ 事務局合わせて4名)でした。高知もこだわってます!
※詳しくはこちら。
2019年06月25日掲載
日本生活中心教育研究会「ちば」の開催について
- ○ 期日:2019年7月20日(土)13:30~16:30
- ○ 会場:植草学園大学L棟
- ○ 内容:
「ムーブメント教育・自立活動の考えを生かした運動プログラムの実践」
「子どもが主体的に取り組む生活単元学習のアイデア」
「講師の先生方を囲んでの分科会(知的障害/自閉症・情緒障害)」 - ○ チラシや申込み方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
2019年06月11日掲載
「第1弾 やってみよう!生活単元学習in金沢」の開催について
- ○ 期日:2019年6月15日(土)9:30~12:30
- ○ 会場:石川県立いしかわ特別支援学校
- ○ 講師:金沢市立押野小学校教諭 山崎麻子先生
- ○ 2019年度は、9月14日(土)、2月22日(土)を予定
- ○ チラシや申込み方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
2019年06月11日掲載
第21回 日本生活中心教育研究会
- ○ テーマ:新学習指導要領とこれからの知的障害教育
- ○ 日時:2019年2月16日(土)13時30分~16時15分
- ○ 場所:植草学園大学
- ○ 内容:シンポジウム
- ○ シンポジスト:坂本 裕(岐阜大学)、佐々木 全(岩手大学)、菊地一文(植草学園大学)、
コーディネーター高倉誠一(明治学院大学) - ○その他:案内及び申込書のダウンロードはこちら
2019年01月24日掲載
12月15日「第13回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会」を開催しました。
12月15日「「第13回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会」が開催されました。
参加者は22名。小学校の知的障害特別支援学級の実践報告、就学相談のあれこれ、弁護士の方による刑務所に福祉施設化のレクチャー等、話題は豊富。元気な様子は、西岡会長がまとめてくださっております。
※詳しくはこちらへ。
2019年01月24日掲載
平成30年度「いしかわ生活単元学習を学ぶ会」の学習会の予定について
- ○ 第1回 6月30日(土)9:30~12:00
- ○ 第2回 12月8日(土)9:30~12:00
- ○ 第3回 3月2日(土)9:30~12:00
-
3回とも
- ・場 所 石川県立いしかわ特別支援学校(金沢市南森本町リ1番1)
- ・講 師 名古屋 恒彦 氏(植草学園大学教授)
- ・内 容 実践報告(各回、実践を2つ報告する予定)と協議
2018年05月28日掲載
第21回 日本生活中心教育研究会
- ○ テーマ:新学習指導要領とこれからの知的障害教育
- ○ 日時:2019年2月16日(土)13時30分~16時15分
- ○ 場所:植草学園大学
- ○ 内容:シンポジウム
- ○ シンポジスト:坂本 裕(岐阜大学)、佐々木 全(岩手大学)、菊地一文(植草学園大学)、
コーディネーター高倉誠一(明治学院大学) - ○その他:詳細が決まり次第、改めて、ホームページにアップします。
2018年04月23日掲載
第18回「日本生活中心教育研究会・ちば」のご案内
- ○ テーマ:実践 生活単元学習・作業学習
- ○ 日時:2018年7月21日(土)13時~16時30分
- ○ 場所:植草学園大学
- ○ 内容
- ・基調提案
- ・実践報告-知的障害特別支援学級「生活単元学習」、知的障害特別支援学校「作業学習」
- ・分科会-「生活単元学習」「作業学習」
- ・まとめ
- ○講師:高倉誠一(明治学院大学)、佐藤愼二(植草学園短期大学)
- ○その他:詳細が決まり次第、改めて、ホームページにアップします。
2018年04月23日掲載
20回日本生活中心教育研究会
第11回とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会
報告「元気がでた!高知で」
日本生活中心教育研究会
会長 中坪 晃一
はじめに~「元気がでる!高知へ!」
「日本生活中心教育研究会」(以下:本研究会)の「第20回研究大会」は、「とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会」(以下:「とさ・りぐる会」)の「第11回研究会」との共催で、平成30年1月27日、高知の地での開催となりました。
本研究会にとっては、事務局のある千葉県外では初の開催、それも、第20回、記念すべき大会でした。
前々から、千葉以外での研究会開催は、話題に上がっていました。高知市での開催は、高知市立高知特別支援学校と高知市・南国市の特別支援学級の確かな実践、頑張りがあってのことです。ご承知のように、全日本特別支援教育研究連盟(以下:全特連)の研究奨励賞を、28・29年度と2年連続で、高知が受賞した実績があるからです。ここ10年近い高知市立高知特別支援学校の実践の積み重ねと、それが波及してか、高知市と、隣の南国市の特別支援学級の質の高い実践の展開がありました。その実践をつなぐ中心に、原動力となった、本研究大会共催の「とさ・りぐる会」の頑張りがあったということです。
加えて、平成12年の全特連の全国大会高知大会で、当時の理事長小出進先生が、「(教育は)卒業後豊かに生きるためではない。今を、明日を豊かに生きる教育。豊かに生きるということの最重要用件は、主体的生きること」(2001;12;18千葉大附養2学期末研修会でのお話し)のお考えで、高く評価された「豊かに生きよう、~今を、明日を、将来を」をテーマに掲げた高知でもあります。
高知開催をお願いした理由は、「元気がでる!高知へ!」でした。
参加・準備状況~「参加者がどのくらいいるか?」
当初、参加者数が懸念されましたが、結果は、岩手・宮城・群馬・東京・千葉・静岡・岐阜・鳥取・福岡・佐賀・高知等の各地から、同志の方々はじめ60名余が馳せ参じてくれました。
天候不順で飛行機が飛ばない中、急遽新幹線に振り替え、徹夜に近い状態で、また、インフルエンザがらみの体調不十分で参加された方もおられました。参加者増に向けて開催市「とさ・りぐる会」の頑張りがあり、また、気持ち溢れる全国の同志の心意気があってのことと、胸熱くなりました。
準備は、本部事務局と「とさ・りぐる会」事務局が連携し合って、進められました。当日の細々した段取り(受付・会費徴収・書籍販売等々)は、全て、「とさ・りぐる会」で見事に仕切っていただきました。「いつもは全部しないといけないのに、楽させてもらった」(本部事務局長の独り言)というほどでした。
研究会の様子~「発表は小学校特別支援学級だけだが」
研究会の主題は、「子ども主体の教育~再考Ⅲ」として、副題を「特別支援学級における学級生活づくり:子どものやりがい・手応えを高めて」でした。
交流及び共同学習の広まりもあり、特別支援学級の生活が不確かになりつつあるという指摘があります。今回、発表者4人は、全員小学校特別支援学級の先生です。それぞれの学級で、本格的な生活単元学習に取り組んだ実践です。発表は、小学校特別支援学級の実践ですが、「子どものやりがいと手応え」の追究は、特別支援学校も、また作業学習も同じです。本質は同じと受け止め、内容の高まりを大いに期待してのことでした。
最初の発表は、福岡市立当仁小学校の北崎裕嗣先生。前任校での実践「わくわくおしごとたいけん~バザーでお店を出そう~」の取り組み。バザーに向け、子どもが計画段階から参画し、その反省・まとめから、毎年子どもが作る目当てがバージョンアップしてく様子を報告。今では、定番単元として年間計画に位置付いており、当日開店間際のテント前には、保護者等の長蛇の列ができるほどに。
2番手は、高知市立鴨田小学校谷雄二先生・南国市立長岡小学校式地真先生・高知市立横浜新町小学校北川浩美先生の3人。3学級の「花壇単元」の実践を、補助具等も持ち込み、それぞれ視点を変えての発表。「とさ・りぐる会」での仲間のつながりで、互いに学級の子ども連れで参観し合ったり、作製方法や材料の入手方法等の情報交換・教材研究、補助具等の提供し合いなども行ったりしながらの取り組み。それぞれに見事な花壇を完成。
その後、本研究会理事でもある植草学園短期大学教授佐藤愼二先生より実践のまとめとして、「新しい学習指導要領とこれからの知的障害特別支援学級・学校」と題して、「Ⅰ『通常の教育』の変革」「Ⅱ『カリキュラム・マネジメント』を学校生活・学級生活づくり論と読み替えて!」、最後に、「知的障害特別支援学級・学校の『教科等を合わせた指導』は、通常学級の『カリキュラム・マネジメント』『教科等横断』のモデルとしての発信を」と、力強いお話しをいただきました。
お客(懇親会) ~「研究会参加者ほぼ全員参加、すごい!」
「特別支援学級」「特別支援学校」の分科会、総会を挟んで、13時30分から「お客」開始。高知では、懇親会・宴会のことを「お客」と言うのだそうです。「いごっそう」「はちきん」による、とことん「接待」の表れでしょうか。
会場は、研究会が実施された「三翠園ホテル」内の「スカイビュールーム」。「三翠園ホテル」自体が、土佐藩主山之内家の別邸・下屋敷で、その最上階が「お客」の場。開始直前にホテルの配慮で、会場変更(当初2階から14階に)となったとか。
「筆山」(山之内家の墓所・桜の名所)を正面に、「鏡川」を眼下に、高知市内を一望できる会場で、50名を超える参加者が、心を通わせ、元気を分かち合う一時となりました。
散会後「ひろめ市場」で2次会。ここにも20名余が繰り出し、高知ならではのつまみを口にしながら、ワイワイガヤガヤ。盛り上がりっぱなしの1日となりました。
まとめにかえて~「来てよかった! 元気がでた!」
隙間の時間・「お客」や2次会等で、耳にした言葉、「来てよかった!」「元気がでた」「思った以上の高知のがんばる姿」「仲間に会えてよかった」「高知はすごい」「エネルギーをもらった」「やる気がでた」……。
本研究大会を、高知で開催できたことは、今後の研究会の在り方を考える上でも、大きな意義がありました。これまで開催地が千葉に固定していたので、各地の研究会からは、数人の方の参加でしたが、今回開催地を変えたら、当該開催地域の方々が参加しやすくなり、顔の見える付き合いが、更に広がりました。他の地域でも是非手をあげて、広げていただければと思います。
本研究会は、手弁当の上に、会員100名程度の小さな研究団体です。しかし、熱のある、思いのある会員ばかりだと、改めて実感しました。研究会の継続・充実・発展の基盤はあると意を強くしました。
しかも会員お一人お一人の背後には、大勢のお仲間がいるはずです。信じたいと思います。身近に子ども主体の教育を、自由でダイナミックな「創造的な実践」を、やりがい感のある教育実践を求める先生方が少なからずいることを。心がつながり、手を結び合えれば、子ども主体の教育の隆盛にもつながるはずと。私たちが、故小出進先生のお考えや教え、それを体現した実践に触れる機会があって、そうなったこととダブりました。加えて、総会で、次期会長として佐藤愼二先生にバトンタッチができ、新役員体制下での本研究会の今後に、期待が大きく膨らみました。嬉しいことでした。
お名前等は失礼しますが、最後に、ご参加いただいた先生方も含め、開催に当たりご尽力・ご協力いただいた全ての方々、又、個人的なつぶやきですが、長年に渡りよいお付き合いをいただいた会員の皆さんに 心からの感謝を込めてお礼申します。ありがとうございました。
今は、「元気を分かち合い、元気が元気の輪を広げる」、これで本研究会は消滅しないと確信し、つなぎの2年が終わりそうでホッとしています。小出先生の墓前に報告します、「生涯、会員でいられそうです」と。
2018年04月23日掲載
第20回「日本生活中心教育研究会」・11回「とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会」共催による研究会を開催いたします(開催日:平成30年1月27日)
 「第20回日本生活中心教育研究会」のご案内を申し上げます。今回は、記念すべき第20回大会でもあり、「とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会」と共催で高知市での研究会開催としました。「子ども主体の教育~再考Ⅲ~特別支援学級における学級生活づくり:子どものやりがい・手応えを高めて~をテーマに、福岡市、並びに、高知県で取り組まれている「子どもとともに、本気、本物」の生活中心教育の実践を発表いただきます。
「第20回日本生活中心教育研究会」のご案内を申し上げます。今回は、記念すべき第20回大会でもあり、「とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会」と共催で高知市での研究会開催としました。「子ども主体の教育~再考Ⅲ~特別支援学級における学級生活づくり:子どものやりがい・手応えを高めて~をテーマに、福岡市、並びに、高知県で取り組まれている「子どもとともに、本気、本物」の生活中心教育の実践を発表いただきます。
また、今回は、実践情報交換会として「特別支援学級」「特別支援学校」の2分科会を設定いたしました。「生活単元学習」「作業学習」の実践や情報交換しながら、「子ども主体の教育」へのお気持ちや思いを参加者全員が思いっ切り語り合っていただきたいと思っております。
学年末のご多用の折とは存じますが、皆さまお誘い合わせの上、是非ご参加いただければ幸いです。
2017年12月24日掲載
日本生活中心教育研究会 会長 中坪 晃一
とさ・子ども主体の学校生活づくりを考える会 会長 西岡ゆき子